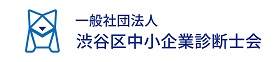中小企業のための生成AIを活用した教育プログラム作成術
多くの中小企業が直面する共通の課題として「人材育成」があげられます。限られた人手や予算の中で、新入社員や若手社員を効率的に育成し、定着率を高めることは容易ではありません。研修プログラムの準備には時間と労力がかかり、ベテラン社員が日々の業務に追われて教育に手が回らず、結果として育成が後回しになるケースも多く見受けられます。
そこで注目を集めているのが「生成AI」の活用です。ChatGPTなどの生成AIを教育現場に取り入れることで、研修教材の迅速な作成、個別最適化された教育コンテンツの提供、社員がいつでも自律的に学べる環境整備が可能になります。すでに国内でも、小規模な企業が生成AIを活用して教育効率の向上や習熟スピードの向上、さらには社員の定着率アップという成果を上げています。
本コラムでは、中小企業が人材育成を効果的に進めるための生成AI活用術を、具体的な事例を交えながら分かりやすくお伝えします。
中小企業こそ生成AIを活用すべき理由
中小企業が人材育成を進めるとき、大きく3つの課題があります。
一つ目は、「仕事のノウハウが特定の人に偏っている」という問題です。
特に中小企業では、経験豊富な社員が持つノウハウが文字などの形で残っていないことが多く、その人が辞めたり異動したりすると、仕事のやり方がわからなくなってしまいます。この問題を解決するためには、生成AIを使ってベテラン社員が持っている知識を素早く文章にまとめる方法が効果的です。AIが支援することで、業務マニュアルなどを短時間で作り、新人や若手に効率よく伝えることができます。
二つ目は、「人材育成にかけられる時間が少ない」という問題です。
中小企業では社員が少ないため、新人の教育に時間を割くことが難しくなっています。そこで、生成AIを使えば、研修資料や業務マニュアルを短い時間で作成できます。また、AI自体を先生や相談役(メンター)として使えば、新人がいつでも質問できる環境を作ることが可能です。これによって教育担当者の負担も減り、効率的に社員を育てることができます。
三つ目は、「社員が自分で学ぶ仕組みがない」という問題です。
多くの会社の研修では、教える側が一方的に話すだけで終わるため、研修が終わった後に内容を忘れたり、実際の業務で役に立たないことがよくあります。生成AIを導入すると、研修後にも社員が繰り返し学べる練習問題やシミュレーションを簡単に提供できます。また、社員自身がわからないことをその都度AIに質問する仕組みを整えれば、自発的に学習を進めることができます。
これらの理由から、生成AIを活用することが、中小企業が持つ「ノウハウが特定の人に偏る問題」「育成の時間不足」「自発的な学習環境の不足」といった課題を解決するための有効な方法になるのです。
| 課題 | 生成AI導入前 | 生成AI導入後 |
| ノウハウ共有 | ベテラン社員に依存 | ドキュメント化され、誰でもアクセス可能 |
| 教材作成時間 | 長い(時間不足) | 短い(迅速に作成) |
| 社員の学習姿勢 | 受け身 | 自主的に学ぶ |
生成AIによる教育コンテンツ作成術
ここからは実際に中小企業で生成AIを活用して教育コンテンツを作る具体的な方法を、3つのシーン別にご紹介します。
シーン①:ベテラン社員のノウハウを教育コンテンツにする
まず、ベテラン社員が持っている仕事のノウハウや知識を生成AIで教育コンテンツにする方法です。これには「インタビュー」を活用します。
- 最初に、ベテラン社員に普段の業務手順や注意点などを話してもらい、その内容を録音します。
- その録音した音声を文字に起こし、生成AIに取り込んで要点をまとめてもらいます。
- AIが作った要点を見ながら、人がチェックして、図や写真を追加すればわかりやすいマニュアルや手順書が短時間で完成します。この方法なら、忙しい社員に負担をかけず、会社に必要なノウハウを効率よく記録して教育に役立てられます。
この方法なら、忙しい社員に負担をかけず、会社に必要なノウハウを効率よく記録して教育に役立てられます。
シーン②:効果的なコンテンツを生成する方法
次に、実際の研修や業務指導に役立つ、わかりやすく効果的なコンテンツを生成AIで作る方法です。
- 最初に、教えたい内容(例えば営業の話し方や製造現場での注意点など)をテーマにして、「新人向けの会話例を作成してください」や「よくある失敗例を紹介してください」などの指示をAIに与えます。
- AIが作成した文章やシナリオを読み、必要に応じて表現を修正したり、図や表を加えてわかりやすく整えます。
- 特に理解しづらい業務については、「よくある質問集(FAQ)」をAIに作成させると、実際に現場で役立つ教材になります。
このように生成AIを使えば、短時間で実践的でわかりやすい研修コンテンツを作ることが可能です。
効果的なコンテンツを作るためのプロンプト(指示)の具体例
| 用途(シーン) | プロンプト(AIへの具体的な指示) |
| 営業トークの教材 | 「新入社員向けに、商談で使えるわかりやすい会話の例を作成してください。」 |
| 製造現場の注意点 | 「製造工程でよく起こるミスとその予防方法を具体的に説明してください。」 |
| 業務シナリオ演習 | 「顧客からのクレームがあった場合の対応手順を具体例で示してください。」 |
| よくある質問集(FAQ) | 「新人社員がよく質問する営業活動の疑問とその回答をまとめてください。」 |
シーン③:社員の自己学習を促進するコンテンツ作成
最後に、社員が自分のペースで学べるようにするための自己学習コンテンツの作り方です。
- 研修後に学んだことを忘れないように、AIを使って「復習用の問題」を作成します。たとえば、「営業トークの穴埋め問題」や「安全管理のチェックリスト」などを作成し、社員が繰り返し練習できるようにします。
- また、社員がわからないことをいつでもAIに質問できるように、「AIチャットボット」を導入します。チャットボットは、社員の質問にすぐ答えられるので、自分で調べる手間が省け、自発的に学ぶ習慣がつきます。
こうして生成AIを活用すれば、社員が仕事に役立つ知識を自分で身につけやすくなり、教育効果が持続します。
このように、生成AIは中小企業のさまざまな人材育成のシーンで役立てることができます。具体的なシーンごとにAIの使い方を工夫することで、教育の質を高めつつ、効率化も図れるのです。
見出し1・2を受け、見出し3では、生成AIを活用して実際に中小企業が人材育成に成功した具体的な事例をご紹介します。
中小企業の生成AIによる人材育成成功事例
事例①:ベテランのノウハウをAIでマニュアル化(精密部品製造業・静岡県)
静岡県にある従業員45名の精密部品メーカーでは、ベテラン技術者の退職に伴うノウハウ継承に課題を抱えていました。特に製造工程の細かなコツや手順がベテラン社員の頭の中にしかなく、新人教育がうまく進まない状況でした。
そこで、この企業は生成AI(ChatGPT)を活用し、ベテラン社員にインタビューを実施しました。その内容を録音して文字起こしを行い、生成AIでわかりやすく整理した上で、「作業標準マニュアル」を短期間で作成しました。
これにより、新人社員が業務を理解するまでの期間が3ヶ月から約1.5ヶ月に短縮されました。また、ベテラン社員が引退した後もノウハウが会社に残り、若手社員が安心して業務に取り組める環境が整いました。
事例②:効果的な研修コンテンツで営業力強化(住宅設計事務所・東京都)
東京都の小規模な住宅設計事務所(従業員約20名)では、新人営業社員向けの営業トークや提案書作成方法の教育が課題でした。少ない人手で研修資料を作る余裕がなく、営業力にもバラつきがありました。
同社では生成AIを導入し、営業でよく使うトークスクリプトや商談シナリオを自動作成。具体的な顧客対応の会話例をAIに作らせ、社員同士でロールプレイ研修を行いました。
また、「よくある質問集」をAIで作成し、営業活動中にスマートフォンで即座に確認できる仕組みを整えました。
その結果、新人社員の営業成績が向上し、営業担当者間でのスキル差も縮まりました。
事例③:自己学習コンテンツで社員の自発的な成長を促進(建設業・東京都)
東京都のある建設会社(従業員数十名)では、新人研修後の定着率の低さが問題となっていました。一方的な研修後、学んだ内容を現場でうまく活かせず、結果として業務に慣れるまでに長い時間がかかっていました。
そこで生成AIを導入し、研修後に復習用の練習問題やシナリオ演習を提供することにしました。また、現場で疑問が生じた時にすぐAIに質問できる「AIチャットボット」を導入したところ、新人が積極的に自己学習をするようになりました。
その結果、新人の業務習熟度が高まり、現場での活躍も早まりました。また、社員自身が積極的に学ぶ習慣ができたことで、離職率の低下にもつながっています。
これらの事例は、中小企業でも生成AIを活用することで、人材育成を効果的に進めることができる具体的な証明です。ぜひ参考にしてみてください。
生成AIを導入する際の課題とその解決方法
ここまで生成AIのメリットや活用事例を見てきましたが、実際に導入する際にはいくつかの課題もあります。ここでは、中小企業が生成AIを導入するときによく直面する課題と、その解決方法について解説します。
課題①:生成AIが出した内容の正確さに不安がある
生成AIは便利な反面、時には間違った情報や誤解を招く表現をすることがあります。特に業務マニュアルや研修資料などでは、内容の正確性が重要です。
【解決方法】
- AIが作成した内容をそのまま使わず、必ずベテラン社員や担当者がチェックする仕組みを作ります。
- 最初から完璧な文章を作るのではなく、「AIで作成したものを人が修正する」という使い方を社内で徹底します。
課題②:社員が新しいツールを使うことに抵抗を感じる
新しい技術を取り入れる際、社員が抵抗を感じたり、操作方法が難しく感じて活用しないケースがあります。
【解決方法】
- まずは小さく始めることがポイントです。特定の部署や業務で試験的に導入し、成功事例を社員に共有します。
- 生成AIの使い方について簡単な研修を行い、操作方法を分かりやすく伝えることで、社員の不安を取り除きます。
課題③:AI活用のためのプロンプト作成に慣れない
生成AIに適切な指示(プロンプト)を出すことが難しいと感じることもあります。曖昧な指示だと望んだ結果が得られません。
【解決方法】
- 最初にプロンプトの簡単なテンプレートを社内で作成し、それを社員が使えるようにします。
- よく使うプロンプトを社内で共有し、うまくいった例を蓄積していくことで、誰でも効果的にAIを活用できるようになります。
課題④:生成AIに業務上の機密情報を入力するリスク
業務で使うAIには、機密情報を入力することによる情報漏洩のリスクがあります。
【解決方法】
- Aあらかじめ社内ルールを決めておき、「AIに入力してもよい情報」と「入力してはいけない情報」を明確にして社員に周知します。
- 情報管理の担当者が定期的にチェックし、安全に運用されているか確認します。
これらの課題とその解決方法をあらかじめ理解し、適切に対応することで、中小企業でも生成AIをスムーズに導入し、人材育成に大きな成果を出すことが可能になります。
| 課題 | 解決策 |
| AIが出した内容の正確性への不安 | AIが生成した内容をベテラン社員や担当者が必ずチェックする仕組みをつくる。 |
| 社員が新しいツールに抵抗感がある | 特定部署から小さく試験導入し、使い方の研修を実施して成功事例を共有する。 |
| AIへのプロンプト(指示)作成が難しい | 簡単なプロンプトのテンプレートを用意し、成功した事例を社内で共有して蓄積する。 |
| 機密情報漏洩リスクがある | 「AIに入力して良い情報」と「入力してはいけない情報」を明確化し、規約上データが学習に利用されないAIサービスを利用する。情報管理担当者が定期的に確認する。 |
これからの人材育成における生成AI活用の展望
生成AIの技術は日々進化しています。ここまでご紹介してきた活用方法は、現時点で既に実現できるものですが、今後はさらに多くの可能性が期待されています。
まず、教育コンテンツ自体がより豊富になり、動画や音声による教材作成も簡単になるでしょう。たとえば、文字情報だけでは理解が難しい作業手順を、生成AIが動画や音声付きで解説してくれるようになるかもしれません。これにより、社員はより直感的に業務内容を理解できるようになります。
また、リアルタイムでAIが社員をサポートする仕組みも広がるでしょう。現場で問題が起きたとき、生成AIが即座に解決策を提案したり、トラブル対応のシミュレーションを提供してくれるようになります。こうしたリアルタイムな支援により、現場の社員が安心して業務に集中できる環境が整うでしょう。
さらに、AIの活用が進むと、社員の学習履歴をもとに、より個別に適した教育プログラムを自動で作成してくれる仕組みも一般化するでしょう。AIが社員一人ひとりのスキルや理解度を把握し、それに応じて適切な教育コンテンツや学習方法を提案することで、効率的な人材育成が実現します。
こうしたAI活用が進むことで、中小企業はますます「人材育成」を経営の強みに変えることができるようになります。
生成AIを上手に取り入れて、社員が自ら学び成長する組織を目指しましょう。
まとめ
中小企業が人材育成で直面する課題に対して、生成AIは効果的な解決手段となります。
ベテラン社員の業務ノウハウの属人化を解消し、教育にかける時間不足を補い、社員自身の自発的な学習を促進することが可能だからです。
具体的な活用シーンとして、ベテラン社員の知識を迅速にマニュアル化したり、効果的な研修コンテンツを作成したり、社員が自己学習できる環境を整備する方法を紹介しました。これらの方法を実際に導入した中小企業では、業務の効率化、社員の能力向上、定着率改善など、さまざまな成果を得ています。
生成AIの導入には課題もありますが、運用ルールを明確にし、情報漏洩への対策やAIサービスの適切な選択を行うことで解決できます。
今後、生成AIの活用はさらに進み、動画やリアルタイム支援など、より高度な人材育成が可能になるでしょう。中小企業こそ積極的に生成AIを活用し、「社員が自ら学び成長する組織」へと進化を遂げていきましょう。
当会のご支援について
当会では経営コンサルティング、IT導入・活用、補助金・助成金などの申請に関するご支援、事業計画書作成などのご支援をしております。
ご相談は、お問い合わせフォームからお願い致します。

お気軽にお問合せ下さい!
お問い合わせ
当会やご支援内容に関するご相談、ご入会に関する申請方法などお問い合わせ下さい。